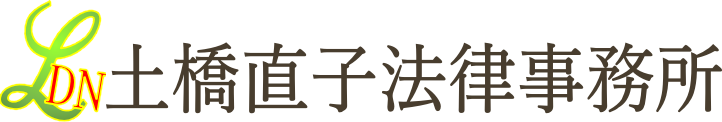平成20年法改正の一環として『法定相続情報証明制度』が新設されました。かなり使い勝手が良い制度なので、お勧めしたく、どんな制度なのか詳しく見ていきましょう。
1 法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は、一言でいうと被相続人の法定の相続関係を一覧図で証明するものです。
法定相続情報一覧図には、被相続人の生年月日・死亡年月日・最後の住所・最後の本籍地、法定相続人全員の生年月日・住民票上の住所(※住所は無くてもOK)が関係図の形で記載されており、この1枚で相続関係がひと目で分かるという優れもの。
~法定相続情報一覧図の写しのサンプル図~
上の図サンプル図のとおり、被相続人・相続人の情報と相続関係がひと目で読み取れる一覧表に、法務局の登記官の記名押印がなされたモノが法定相続情報一覧図です。
2 法定相続情報一覧図を取得するメリット
(1)メリットその1 相続手続が簡単になる!
これまでは、相続関係を証明するためには被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本と、それに繋がる各相続人の戸籍謄本までを全て入手して、相続手続を行う役所や金融機関等に個別に提出しなければなりませんでした。
例えば、被相続人名義の預金口座が、A銀行・B銀行・C銀行それぞれに有った場合、相続手続のためには、まずA銀行に戸籍類を提出してコピーを取ってもらって返却を受け、次にB銀行に戸籍類を提出して・・と、順繰りに手続せざるを得ず、しかも戸籍謄本の有効期限は一般的に発行から3か月以内(金融機関によって異なる)なので、あちこち手続しているうちに有効期限が過ぎて、再度戸籍謄本を取り寄せなければならなくなる、なんてことが頻繁にありました。
他方、法定相続情報一覧図が有れば、戸籍類を提出する代わりに一覧図1枚を提出すれば相続人であることが証明でき、金融機関にその場でコピーを取ってもらって返却を受けてすぐに次の金融機関に提出することが可能です。
さらに、法定相続情報一覧図は一度に5枚まで交付してもらえる(再交付も可能)ので、複数の相続手続を同時進行させることも出来るうえ、戸籍謄本と違って基本的に有効期限もありません。
(2)メリットその2 費用がかからない!
この法定相続情報一覧図は、なんと「無料」です!法務局さん太っ腹・(いや、あちらにも狙いがあるようですが・・・)
もちろん、法定相続情報一覧図の交付を受けるためには、一度は被相続人の出生から死亡まで&法定相続人全員の戸籍類を集める必要がありますが、その後の相続手続が段違いにスムーズに進められるので、特に相続関係が複雑な場合や、法定相続人が多数の場合などは膨大な量の戸籍類を抱えて走り回る手間を省く観点からも取得するのが良策です。
3 法定相続情報一覧図の取得方法
(1)法定相続情報一覧図はどこで取得する?
管轄法務局に申請します。管轄法務局は、
- 被相続人の最後の住所地(死亡時に住民票がある住所)
- 被相続人の最後の本籍地
- 被相続人名義の不動産の所在地
- 申出人の住所地
の❶~➍のいずれかを管轄する法務局が該当します。4つの中からどの法務局でもOKなので、自宅や職場から一番近い法務局を選択しましょう。管轄が判らない場合はこちらからチェックしてください。

郵送でも申請できますが、書類に不備や不足があると、その都度内容の訂正や追加書類を郵送する羽目になるので(結構な確率で訂正・補正を指示されます)、近くに管轄法務局がある場合は、直接窓口で手続した方が早いです。
(2)法定相続情報一覧図の取得に必要な物・書式
②法定相続情報一覧図(の原稿)書式(Excel)一覧はこちら→(主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例)
③相続関係を証明する戸籍謄本類一式
④被相続人の除票(または戸籍附票)
⑤法定相続証明に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票(または戸籍附票)
※以下は、代理で請求する場合に上の書類に加えて必要になります。
注)代理人になれるのは,親族の他、弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士です。
⑦代理人の印鑑・身分証明書の写し
⑧委任者の身分証明書の写し(※原本確認文言に注意!下図を参照)又は住民票

法定相続情報一覧図の申請必用書類 まとめ
- 法定相続証明申出書
- 法定相続情報一覧図(の原稿)
- 相続関係を証明する戸籍謄本類一式
- 被相続人の除票(または戸籍附票)
- 法定相続証明に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票(または戸籍附票)
※代理で請求する場合、上の書類に加えて - ①代理人への委任状
②委任者の身分証明書の写し(※原本確認文言に注意)又は住民票
③受任者(代理人)の印鑑・身分証明書の写し - ※郵送で請求する場合、返信用封筒(レターパック+がお薦め)
4 法定相続情報一覧図の主な使途
- 銀行や証券会社に、戸籍謄本の替わりに提出
- 不動産の相続登記の際に、戸籍謄本の替わりに提出
- 相続税の申告時に、戸籍謄本の替わりに提出
相続人側から見れば、いちいち戸籍謄本を全部提出する手間を省けますし、提出を受ける側も、場合によっては膨大な量になる戸籍謄本を全部コピーしなくて済むのでありがたい制度です。
5 再交付を希望する場合
相続税申告等で法定相続情報一覧図を提出した後で、一覧図が足りなくなって再度交付を受けたい場合は、5年以内(※申出日の翌年から起算)なら再交付してもらうことができます。
再交付申出書の書式はWordアイコンを、記入例はPDFアイコンをクリック

では、再交付を申請する前に申出人が死亡してしまった場合は、もう誰も再交付を受けることが出来ないのでしょうか?

法務局のホームページには書かれていませんが、申出人が死亡してしまった場合は、5年以内の要件を満たすなら、その申出人の相続人が、相続人であることを戸籍謄本等で証明すれば再交付を受けることが出来ます。
いかがですか?法定相続情報証明制度は、必要書類が多くて一見面倒に感じられるかもしれませんが、やってみると意外に簡単に手続できる制度です。
分からないことがあれば、管轄法務局の担当者に窓口や電話で質問するか、法務局のホームページ(こちらをクリック)で確認できます。もちろん、相続関係が複雑だったりして一覧図の作成が大変そうなら、私たち弁護士等の専門家に聞いてください。いつでもアドバイス致します!
投稿者プロフィール

最新の投稿
 暮らしと法律2021年4月10日法定相続情報証明制度とは?制度と手続方法を書式付きで徹底解説
暮らしと法律2021年4月10日法定相続情報証明制度とは?制度と手続方法を書式付きで徹底解説 暮らしと法律2021年3月16日相続ガイド1 相続人は誰?相続人の範囲と順位
暮らしと法律2021年3月16日相続ガイド1 相続人は誰?相続人の範囲と順位  事例紹介2020年5月15日沖縄の土地の相続 軍用地って価値があるの?
事例紹介2020年5月15日沖縄の土地の相続 軍用地って価値があるの? 事例紹介2020年5月15日国選弁護 否認事件の事例 覚醒剤「シャブちゃいます、○○やで?!」
事例紹介2020年5月15日国選弁護 否認事件の事例 覚醒剤「シャブちゃいます、○○やで?!」