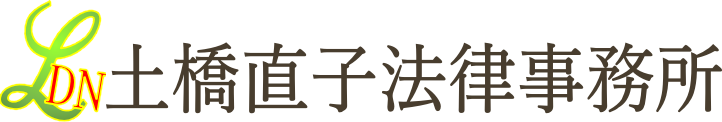身内が亡くなったら、相続はどうなる?
相続は、親兄弟姉妹が死亡した場合に、誰でも直面する問題です。
そんな相続について、手続の流れとともに抑えておいた方がいい点について解説してみます。
1 死亡→死亡と同時に相続が発生する
親族が死去すると、その死亡の時点で相続が発生します。具体的には、死亡の時点の亡くなった方(被相続人)の所有財産が相続財産となり、死亡の時点で相続の権利を持っている人が相続人となります。
2 相続人の範囲と法定相続分
相続には順位が定められており、
(1)第1順位 配偶者と子供(直系卑属)が相続人

図のとおり、被相続人に配偶者(夫、妻)と子供がいれば、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子供の人数で割った分を子供が相続します。
第1順位で、配偶者が死亡又は離婚で存在しない場合でも、直系卑属(子供や孫)が1人でもいれば、その人物が相続人となり、第2順位の相続はありません。
(2)第2順位 配偶者、両親・直系尊属

被相続人に子供がいなかった場合は、配偶者が3分の2、被相続人の両親が残りの3分の1を2人で相続します。
第2順位で、被相続人の直系尊属(両親・祖父母・曽祖父母)の1人でも存命であれば、第3順位の相続はありません(まあ、祖父母等が孫を相続するのは稀ですが)。
(3)第3順位 配偶者、兄弟姉妹・兄弟姉妹が死亡している場合はその子

直系卑属も直系尊属も存在しない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
図は同じ両親を持つ兄弟姉妹が相続するケースですが、下の図のような場合は、相続分が違ってきます。

図のように、被相続人との血の繋がりが片親だけの兄弟姉妹の相続分は、両親とも同じ兄弟姉妹の2分の1となります。
3 代襲相続

相続人となるべき人が、被相続人より先に死亡していた場合でも、子供がいればその子供(被相続人から見て孫)が代わりに相続人となります。もし、その子供も先に死亡していても、その子に子供がいれば(被相続人から見てひ孫)、ひ孫が相続人となります。このように、親や祖父母に代わって相続することを代襲相続(再代襲相続)と言います。
注)ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合で、被相続人より先に死亡していた場合は、その兄弟姉妹の子供が親に代わって相続人となりますが(被相続人から見て甥姪)、甥姪も被相続人より先に死亡した場合、その甥姪の子供は代襲相続人にはなれず、相続はそこで終わります。
法定相続分をもう一度確認してみましょう。
民法上定められた被相続人の遺産を相続する割合(=法定相続分)は、次のとおりです。
(1)配偶者(夫又は妻)と子供が相続人の場合
配偶者が1/2、子供が残りの1/2を人数割で相続します。
(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が2/3、直系尊属が残りの1/3を人数割で相続します。
(3)配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4を人数割で相続します。
4 相続関係の調査方法
相続人の戸籍謄本を取り寄せて、転籍してきている場合は、前の戸籍、その前の戸籍と追いかけ、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全部集めて、相続人が誰になるか判断します。
戸籍謄本の種類、取り寄せ方法
→本籍地を管轄する市町村の役所にの窓口又は郵送で請求します。郵送の場合、返信用の封筒と手数料分の郵便小為替(戸籍謄本450円/1通、除籍謄本・原戸籍謄本750円/1通)を同封します。
戸籍謄本の請求書や具体的な送付先は、「○○市(区)役所 戸籍謄本 郵送請求」で検索すれば各役所のホームページに説明が出てきます。
もし、本籍地がどこか分からなかったら、本籍地の記載ある住民票を住民票登録のある市町村で請求すれば確認できます。
-
なぜ、出生から死亡までの全部の戸籍が必要なのですか?
-
被相続人が結婚、離婚を繰り返して前婚で子供が生まれていたり、認知した子供がいたりした場合、相続関係が変わる可能性があるからです。
自分に兄弟姉妹はいないと思っている人が戸籍を調べたら、父親と前の奥さんとの間に子供がいることが判明して、母親違いの兄弟との共同相続になった、なんて結構よくある話です。
また、どちらが先に死亡したのかでも相続関係は変わってきますので、死亡年月日の確認のためにも生まれてから死亡までのすべての戸籍をそろえる必要があるわけです。
-
戸籍謄本以外に除籍謄本や原戸籍謄本が必要と言われたのですが、除籍謄本・原戸籍謄本とは何ですか?
-
除籍謄本
←その戸籍に載っていた人が死亡あるいは転籍で抜けて全員いなくなった場合、その空っぽになった戸籍が除籍と呼ばれます。
原戸籍謄本
←原戸籍(改正原戸籍)というのは、平成6年の法改正に基づく同年の法務省令により、戸籍の電子データ化が開始され、それまでの縦書き・手書きの戸籍は電子データ化した横書きの戸籍に戸籍が作り替えられ、それまでの縦書き・手書き戸籍は、お役目終了で『生き埋め』になりました。
この、電子データ化した戸籍の元となった‟生き埋め戸籍”のことを改正原戸籍と呼びます。ちょっと面倒なのは、電子データ化しようという法律&法務省令自体は平成6年なのですが、実際の電子データ化は役所ごとに入力の時期が異なるため、平成20年を過ぎてから電子データ化した戸籍も多く、電子データ化する以前の戸籍関係を調べるためには改正原戸籍も確認する必要がある点です。
(なお、厳密には昭和23年1月1日の新戸籍法施行以前の戸主制度の戸籍も昭和改正原戸籍と言いますが、ここでは割愛します。)

ちなみに、大阪市内で転籍している場合は、市内のどこの区役所でも、市役所の証明書発行センターでも、まとめて戸籍・原戸籍・除籍謄本を請求することが出来ます。
例えば、天王寺区の戸籍謄本や原戸籍・除籍謄本を中央区役所の窓口で請求しても、役所のデータはオンラインで繋がっているのでちゃんと交付してもらえますよ。
~アメリカ合衆国(U.S.A)では相続の調査はどうするの?~

アメリカは戸籍制度が無いんですよね?
相続関係はどうやって調査するんでしょうか。

私も実際に調査した経験はないのですが、NYの弁護士資格
(アメリカは州ごとに弁護士資格を取得)を持っている弁護士の話では、
凄い調査方法があるそうです。

え!いったいどんな方法ですか?

それは・・「ネットで検索」!
は・・・?(びっくりして顔が出ない)

要するにアメリカは、公的機関ではなく民間の情報管理業者が個人の親族関係のデータベースを保管していて、それをネット検索するわけです。住所、氏名、生年月日等を入力すると、データベースに登録された情報がヒットします。で、さらに詳しい情報を調べようとすると、
「これ以上の情報が必要なら、 ○○ドルお支払いください?」
という画面になるという・・・(笑)
なんでもビジネス?のアメリカらしい方法ですね。
まあ、役所が管理するか民間業者かの違いって考えれば違和感もそんなに・・でも、欧米人の名前ってただでさえ同姓同名多そうだし、間違いとか無いんでしょうか・・・なお、相続関係については、調査結果に間違いがないことを確認するために、公証人に頼んで『宣誓供述書』を作成することも多いようです。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 暮らしと法律2021年4月10日法定相続情報証明制度とは?制度と手続方法を書式付きで徹底解説
暮らしと法律2021年4月10日法定相続情報証明制度とは?制度と手続方法を書式付きで徹底解説 暮らしと法律2021年3月16日相続ガイド1 相続人は誰?相続人の範囲と順位
暮らしと法律2021年3月16日相続ガイド1 相続人は誰?相続人の範囲と順位  事例紹介2020年5月15日沖縄の土地の相続 軍用地って価値があるの?
事例紹介2020年5月15日沖縄の土地の相続 軍用地って価値があるの? 事例紹介2020年5月15日国選弁護 否認事件の事例 覚醒剤「シャブちゃいます、○○やで?!」
事例紹介2020年5月15日国選弁護 否認事件の事例 覚醒剤「シャブちゃいます、○○やで?!」